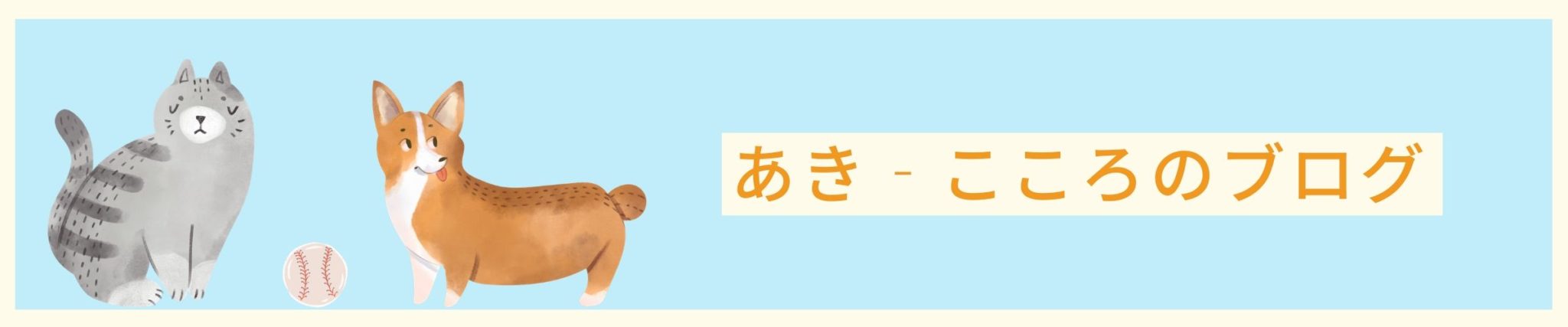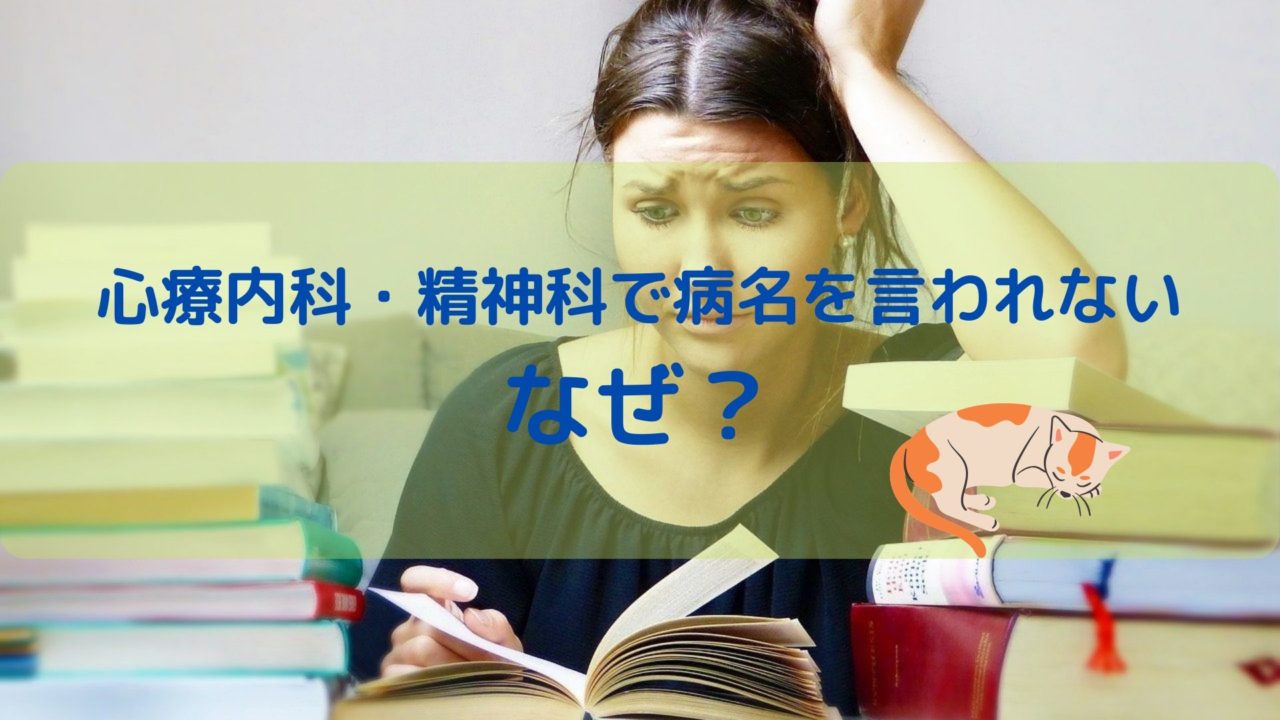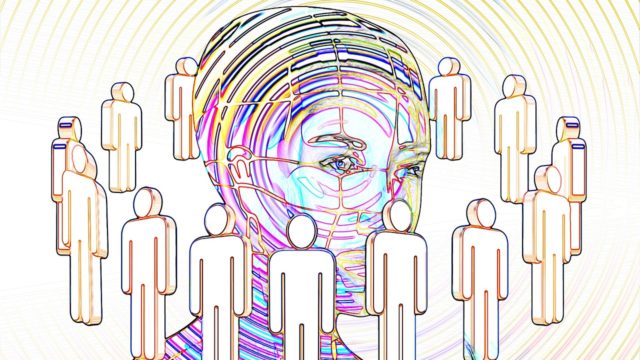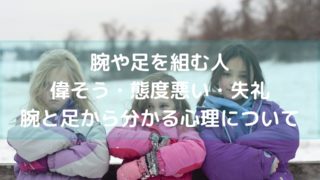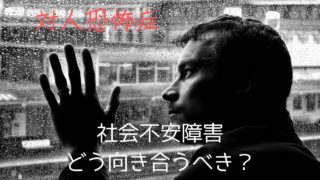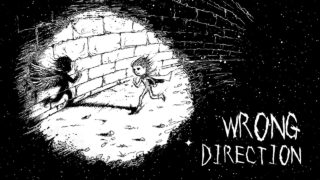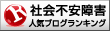こんにちは、あきです。
心療内科や精神科に何度か通っていて病名を一向に言われないと、不安に感じてしまいますよね。
僕も実際に、初めて通った精神科以外では、ハッキリと病名を言われたことがありませんでした。
初診で必ず「社会不安障害かもしれない」「こんな症状を今まで抱えてきた」といったことを話してきましたが、「そうなんですか」「大変でしたね」くらいしか言われず、病名は言われることはありませんでした。
長いこと「なんで病名をハッキリ言ってくれないんだろう」と疑問に思っていたものです。
しかし、良い心療内科・精神科の先生ほど病名を言わないし、ハッキリとした診断はされません。
逆に、患者のことを考えていないような自分勝手な精神科医ほど、病名を付けて薬をたくさん処方したがります。
僕は今までに3つの心療内科・精神科に通ってきたのですが、1番最初に通った心療内科・精神科は非常に最悪なところでした。
こちらの病院では最初の診察でハッキリと病名を診断されましたし、こちらの話を聞かずに強い薬を色々と出されたものです。
その病院について書いた記事もあるので、良かったら下記のリンクから読んでみて下さい。
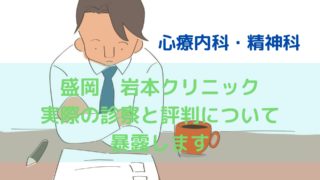
しかし、ちゃんとした心療内科・精神科では病名を言われることはほとんど無いと思います。
この記事では、心療内科・精神科でハッキリとした病名を言われない理由について書いていきます。
また、僕がおすすめしている心療内科やおすすめできない心療内科の特徴について、以下の記事で書いています。
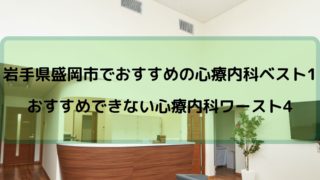
心療内科・精神科で病名を言われない、診断されないことに不安を感じている方へ

ツイッターなんかで病み垢や闘病垢を見ていると、自身の抱えている精神疾患の病名をたくさん並べている人がいます。
また、ツイートで自身の飲んでいる薬の名前をたくさん並べたりしていて、情報交換なんかを望んでいる人もいます。
傍から見ていると、みんなハッキリとした病名を聞くことが好きだし、薬にも拘りが強いように思います。
しかし、心療内科・精神科で病名を診断しても、何の解決にもなりません。
厳しい言い方ですが、これは、辛くて苦しい状況を乗り越えるためにも必要な考え方であり、真実だと思っています。
そのことについて深掘りしていきます。
病名を診断しても、何も解決できない
確かに、心臓病や脳機能障害のような直接命に関わり、治療法が確立しているようなものであれば、ハッキリと診断することは必要になります。
しかし、明確な治療法が無い状態で診断をしても、患者にとっては不安でしかありません。
心療内科・精神科ではこれと言った病名もハッキリとしないし、その治療法もハッキリとしたものがあるわけでもないです。
明確な治療法が無いために、患者の不安が取り除かれることは永久にありません。
なので、僕たち患者は「診断」ではなく、今現在抱えている「症状」に拘るべきなのです。
心療内科・精神科ならではの特徴
今現在、心臓や脳の病気で症状が悪く、死にそうな状態になっているのであれば今すぐ病院に行き、診断を受けたり手術をしてもらうというのは正しいことです。
精神疾患も確かに、今現在本当に苦しくて「今すぐなんとかしてほしい」と思っている方が多いと思います。
しかし、心療内科・精神科では「症状を改善していく」ということの方が重要になってきます。
その病名で正しかったかというのは、その病気が治った時にしか分からないので、最終的な診断をその場ですぐに言うということはできません。
社会不安障害の薬を処方し続けて症状が良くなった時に初めて、「この仮説が正しかった」と分かります。
精神科医が診察の際に患者の話を聞き、そこから「もしかするとこの病気なのではないか」という仮説を立てて薬を処方していきます。
こうした経過の中で診断していく(仮説を立てていく)というのが、心療内科・精神科ならではのやり方になります。
なので、心療内科・精神科で病名を全然言われないということは全くおかしいことでは無いので、安心してほしいと思います。
今まで、色んな病気の薬を処方されてきました
診察の度に先生を見ていて思うのですが、心療内科・精神科の先生は本当に、毎回手探り状態で患者の状況を元に病名を予想したり、薬を処方しているように思います。
僕は中学1年生の頃から社会不安障害の症状があり、軽度の強迫性障害もあるのですが、今まで双極性障害の薬をやパニック障害である母と同じ薬を出されたことも何度かあります。
「出された」と言うと言い方が悪いですが、こういったことは上でも述べた通り、心療内科・精神科では当たり前のことなのです。
患者の話に耳を傾ける
↓
病名、その人に合いそうな薬を予想する
↓
実際に処方してみて、数週間・数か月の経過を見てみる
↓
合っていなかったらまた別の仮説を立てる
↓
合っていたら仮説が正しいので、その薬を処方し続けて再び様子を見てみる
当たり前だし、良い精神科医ほどこのようなやり方を取ると思います。
患者の症状を聞いて色んな薬を試してみるほかありません。
心療内科・精神科では、すぐに病名を断定したがるような医者ほど、信用できないイメージがあります。
ツイッターでも病名をたくさん並べている人ほど病んでいる傾向にあるし、パニック障害である母が今まで通ってきた病院でも、病名を決め付ける医者ほど話を聞かなかったり間違った薬を維持でも処方し続けたりしてきました。
なので、良い精神科医ほど、最終的な病名をすぐには判断しません。
最初に大体のイメージはすると思いますが、後で違ったということも全然あり得るので、
- 抗うつ薬が効いたらうつ病
- SSRIが効いたら不安障害など
このように、初診で病名の仮説を立て、薬を処方してみて仮説が正しいかを確認するものだと思います。

心療内科・精神科でハッキリとした病名を言わない医者ほど信用できる

既に述べましたが、ハッキリとした病名を言わない精神科医ほど、ちゃんと目の前の患者の病気に向き合ってくれています。
診断名を言われないのは、何もおかしいことではない
半年経っても1年経っても一向に病名を言われないというのは不安かもしれませんが、何もおかしいことではありません。
ごくごく当たり前のことです。
診断名を言っても患者が不安になるだけなのを分かっているし、安易に病名を言ってしまうとネットで勝手に調べたりしてネガティブに捉えたり間違った情報を取り入れてしまう人もいます。
精神的な病気は特に、治ったときに初めて病名が分かるので、治療の段階では100%正しいかなんて分かりません。
もしかすると僕の場合も、社会不安障害ではない別の病気だったり、自分が知らないだけで複数の病気があるかもしれません。
いずれにしても、色々な精神療法や薬物療法を試してみて症状が良くなることに重きを置いていくしかありません。
症状が良くなりさえすれば、何の病名かなんてことはそんなに重要ではありません。
慎重で患者のことを考えている先生ほど言わない
以上のことから、慎重で患者に対して気配りをできる精神科医ほど、病名を言いません。
言うのは簡単ですが、それが正しいかは治ったときに初めて分かるので、それまでは誰にも分からないものです。
良い精神科医は、「この人のこの症状はこういう病気の圏内だな」とイメージを持ちながら仮説を立てていきます。
もちろん、最初に予想した病名が変わることもあります。
重要なのは、病名を「言うか言わないか」ではなく、病院に来た時より症状が良くなっているか良くなっていないかということです。
最初より良くなってれば良い傾向だし、悪くなっているのであれば見直すべき。
なので、心療内科・精神科での診断はそんなに気にしなくても大丈夫です。
病名を断定してしまうと、患者だけでなく精神科医もそれに捉われてしまい、正しい治療が行えなくなります。
慎重で目の前の患者のことを考えている精神科医ほど病名を言わないし、言わない先生ほど信頼できると考えられます。
あくまで、重要なのは「最初より良くなっているか悪くなっているか」ということなので、病名ではなく日々の症状を注意深く観察し、それを主治医に伝えていくことが、治療の上で一番大切なことだと思っています。
他にも様々な記事を書いていて、「そんな病気なんてものはないんだよ」と患者に対して言ってくる極端かつ最低なお医者さんの話も以下の記事で書いているので、ぜひ読んでみて下さい。

緊張を和らげる方法なんかについても書いています↓